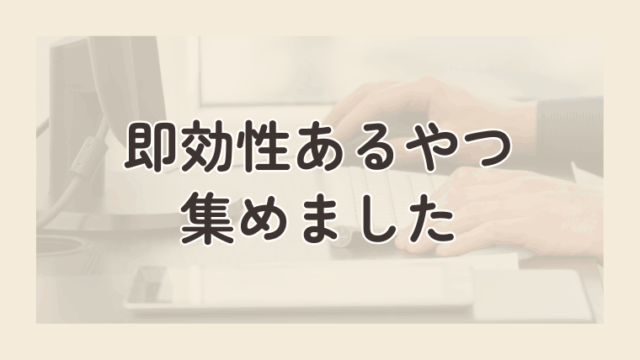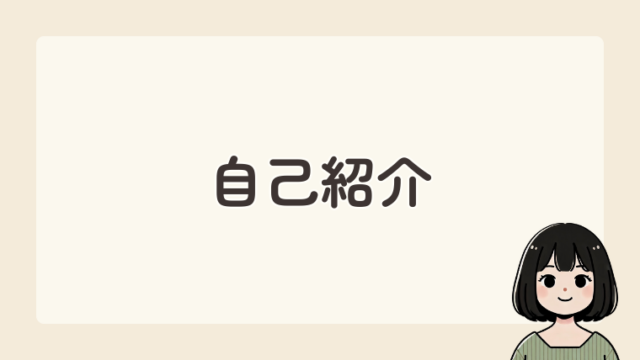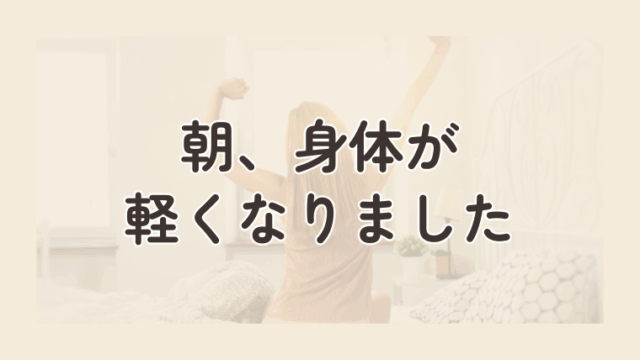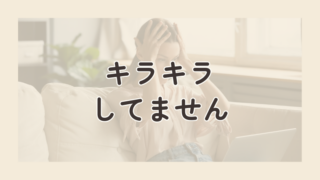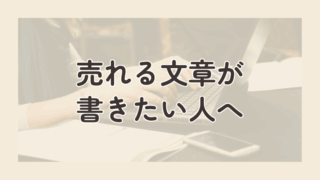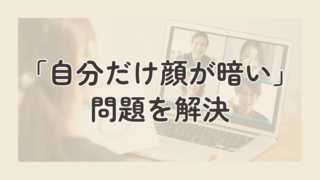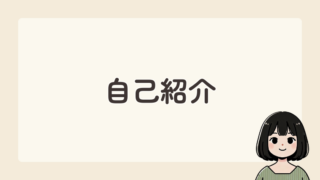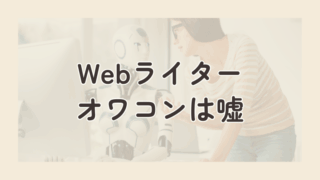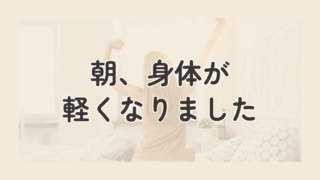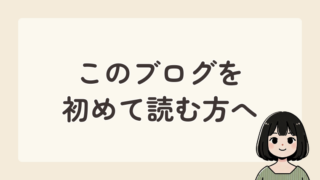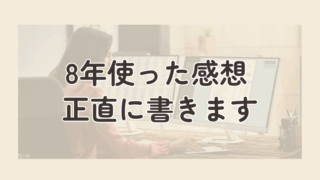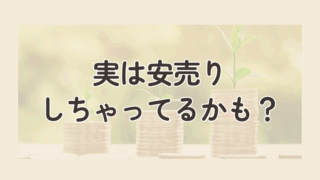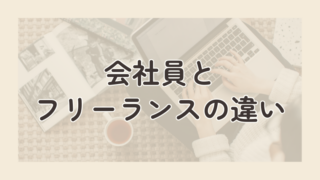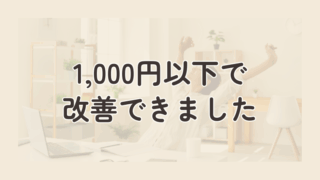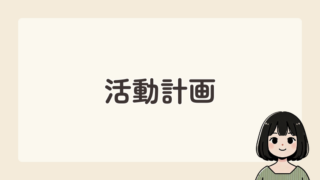こんにちは。
結婚願望なしの34歳独身オンナ「いが」です。
あなたには、こんなお悩みありませんか?
・周りからは「結婚!結婚!」と言われるけど、一人の方が楽で独身生活中
・でも、既婚子持ちの友人とつい比較してしまって、寂しく感じる時がある
・結婚しない選択肢が濃厚なのに、独身で生きていく対策は全くできていない
最近は、「結婚しない人生もアリだよね」と世間の空気が少しずつ変わってきています。
しかし、それでも世の中は基本的にまだまだ「結婚して、誰かとペアになって生きていく」ことを前提に設計されたまま。「女性が一人で生きていく」というライフプランは確立されていません。「独身のまま生きていくには、老後は一体どうしたら…!?」と途方に暮れている女性は、実は結構いるのではないでしょうか。
独身だと、「金銭的・精神的に家族と支え合える(特に老後)」という結婚のメリットが得られないので、とりわけ「お金」と「孤独」の対策をしないといけないと思います。
そこで本記事では、「結婚しない人生を生きる女性の『老後のお金』『孤独』対策」についてまとめました。
「なんとなくこのまま独身で生きていきそうだけど、何の対策もしていない…」
そんな方は今こそ、この問題に向き合う時。ぜひ最後までお読みください!
独身女性の老後はいくら必要?

では早速、まずは「老後の費用」について紹介していきます。
ここから、とっても現実的な話をします…!でも、「独身の人生を謳歌したい!」と思っている方は、目を背けずにじっくり読んでいってほしいです。
生活費
総務省統計局の家計調査報告(2021年)によると、65歳以上の独身女性の1ヵ月あたりの生活費は、平均して14万円弱。
この生活費に加え、税金もかかるため、毎月の支出としては約15万円が想定されます。
女性の平均寿命は87歳。となると、老後には65歳~87歳の約22年間の生活費がかかり、
月15万円 × 12ヶ月 × 22年 = 約3,960万円
が必要になります。
医療・介護・住居・葬儀など生活費以外の費用
さらには、老後には身体が弱ってくることや、人生の締めくくりが近づいていることから、生活費以外にも様々な費用がかかります。
■医療費:約211万円
・月8,000円×12ヵ月×22年=約211万円
・医療サービスを受ける機会が増える75歳~87歳の22年分を仮定
■介護費:約542万円
(月々の介護費用9万円)×(介護期間55ヵ月)+(一時費用47万円)
■住居費
・持ち家の場合:100〜300万円(リフォームやメンテナンス費)
・賃貸の場合:家賃6万円の場合…約1,584万円(22年分)
■葬儀・お墓の費用:約274万円
・葬儀費用:118.5万円
・お墓の購入費用(一般墓):155.7万円
*出典
・公益財団法人生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」
・株式会社鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」
・株式会社鎌倉新書「第16回 お墓の消費者全国実態調査(2025年)」
年金はいくらもらえるのか
ここで思い出したいのは年金です。
今、頑張って年金を払っているのは、老後の費用を助けてもらうためですよね。ここまでに書いた金額を、すべて自分で賄わなければいけないわけではありません。
令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、独身女性の毎月の年金平均受給額は次の通り。
- 厚生年金:約11.1万円
- 国民年金:約5.2万円
この金額で算出すると、老後22年間でもらえる年金額の合計は、
・厚生年金:約2,930万円
・国民年金:約1,373万円
となります。
独身女性の老後に備えて準備したい金額
ここまでの情報をまとめると、独身女性が老後に向けて備えておきたい金額は、次のように算出できます。
■賃貸の場合
・厚生年金の人:約3,641万円
必要額(約6,571万円)-年金収入(2,930万円万円)=約3,641万円
・国民年金の人:約5,198万円
必要額(約6,571万円)-年金収入(約1,373万円)=約5,198万円
■持ち家の場合
・厚生年金の人:約2,157万円〜2,357万円
必要額(約5,087万円〜5,287万円)− 年金収入(約2,930万円)=約2,157万円〜2,357万円
・国民年金の人:3,714万円〜3,914万円
必要額(約5,087万円〜5,287万円)− 年金収入(約1,373万円)=3,714万円〜3,914万円
なお、ここまでの金額は様々なデータの平均値などから計算したものなので、もちろん仮定の金額です。ただそれでも、「老後は相当お金かかるぞ」というのは伝わったのではと思います。
独身女性の老後の費用、どう備えるか?

あまりに生々しくシビアな金額を目の当たりにして、引いてしまったでしょうか…!しかし、老後に向けて今から準備できることや対策は実はいろいろあります。
貯蓄をする
自動積立定期預金
毎月決まった日に普通預金口座から自動的に一定金額を引き落とし、定期預金として積み立てていくサービスです。
・自動引き落としで確実に貯蓄できる
・1,000円から積立可能な銀行が多く、気軽に始められる
といったメリットがある一方で、
・インフレの影響を受けやすい
・お金を大きく増やせず、運用リターンは期待できない
・保証される金額に上限がある
などのリスクも。
財形年金貯蓄
給与や賞与から天引きで積み立てて、将来の年金資金をつくるための制度です。積み立て期間は5年以上、受け取り開始は60歳以降になります。
・給与からの天引きなので、確実に積み立てられる
・利子は非課税(上限あり)
・勤務先に手続きしてもらえる
というメリットがありますが、勤務先が制度を取り入れていない場合は利用できません。
資産形成をする
より大きな老後資金をつくるには、ただお金を貯めるだけでなく、お金に働いてもらう「資産形成」も検討したいところです。
本記事では、特に注目されている「iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)」と「NISA(ニーサ/少額投資非課税制度)」を取り上げます。
iDeCoとNISAとは
iDeCoとNISAは、どちらも利益が非課税になる資産形成方法です。
通常、投資は利益が出ると約20%の税金がかかりますが、iDeCoとNISAはこの税金が免除になるというメリットがあります。
投資信託や株式など、金融商品を自分で選んでいくため、金融の知識が必要になります。
iDeCoとNISAの違い
iDeCoとNISAには共通点はあるものの、違いもあります。違いを表にまとめてみました。
| 項目 | iDeCo | NISA |
| 目的 | 老後資金づくり | 資産形成(目的は自由) |
| 非課税対象 | 運用益 + 掛金の全額が所得控除対象 | 運用益のみ非課税 |
| 拠出限度額(月) | 自営業:6.8万円、会社員:1.2万〜2.3万円など | 年間360万円(成長投資枠240万+つみたて枠120万) |
| 非課税期間 | 60歳まで解約不可(=非課税期間も60歳まで) | 無期限(2024年から) |
| 引き出し制限 | 原則60歳まで引き出せない | いつでも引き出せる |
| 加入条件 | 原則20歳〜60歳(65歳まで拡大中) | 日本に住む18歳以上ならOK |
| 口座数 | 1人1口座(iDeCo) | 1人1口座(NISA) |
・iDeCoは、掛金が全額、所得控除の対象になるが、60歳まで引き出せない
・NISAはいつでも引き出せるが、運用で出た利益のみ非課税(掛金は控除の対象にならない)
という大きな違いがあります。
節税しつつ老後資金をしっかり貯めたい人はiDeCo、中長期的な資産形成をしつつ必要になった時に自由に使いたい人はNISAが向いています。どちらも一長一短ですね。
可能なら、iDeCoとNISAを併用できると理想的。iDeCoで確実に老後資金を準備しつつ、NISAで老後以外にも使える資金を柔軟に運用していけます。
保険に加入する
個人年金保険
公的年金に上乗せして、老後の収入を確保するための保険です。一定期間、保険料を払い込み、60歳以降などの設定した年齢から、毎月または一括で年金として受け取ります。
「保険会社がどのように運用してお金を確保するか」によって、大きく2種類に分けられます。
■定額型
・契約時に受け取る年金額が決まっている
・保険会社が安全な資産で運用
・「インフレに弱い」「利息がほぼ期待できない」などのデメリットも
■変額型
・保険料を投資信託などで運用するタイプ
・将来の年金額は運用成績によって増減する
・「損をするかも知れない」「受け取れる額が確定していない」などのデメリットも
終身保険
一生涯の死亡保障がある保険です。
「死亡時に遺族へ保険金が支払われる」というタイプの保険なので、「配偶者や子どものいない独身女性には向かないのでは?」と思われるかも知れません。
しかし、解約して現金化できるタイプの保険を選ぶと、ある程度の金額が途中で引き出せます。60代〜70代頃で「やっぱり今、手元にお金が必要!」という事態になったら、解約して生活費や医療費に充てるという使い方ができるんです。
また、解約せず死亡時まで利用した場合は、自分の葬儀代やお墓代として残すことも可能です。
介護保険
40歳以上のすべての人が加入する「公的介護保険」でカバーできない介護費用を補う民間の保険です。公的介護保険の自己負担(1〜3割)を補う形で設計します。
介護状態になった時、一時金や年金形式で給付金を受け取れます。若いうちに加入すると保険料が割安になるので、早めに検討しておくメリットはあるといえるでしょう。
年金の繰り下げ受給をする
これは老後になってから出来る対策にはなりますが、「年金の繰り下げ受給」という手もあります。
これは、「年金の受給開始年齢を65歳以降に遅らせると、受給額が増額する」という制度です。受給額は1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増加し、最大75歳まで繰り下げ可能。
「65歳になったけど、案外まだ元気に働ける!」という状態なら、老後資金をさらにプラスする策として有効ではないでしょうか。
結婚しない人生の「孤独」対策

独身で生きていくとなった時、お金と同じくらい大事なのが「人とのつながり」。自分の家庭を持たない分、人とのつながりを自分からつくりに行く姿勢が大切です。
働けるうちは働く
元気なうちは働きに出ることも、実は孤独対策の一つ。
働いていると、職場や取引先など様々な人との交流が自然に生まれますし、仕事で忙しくしていると孤独を感じている暇もなくなります。
その上で収入も増えるなら、働くことは一石三鳥くらいのメリットがあります。
シェアハウスに暮らす
シェアハウスで生活するという選択肢があります。若者~高齢者まで様々な年代の人が一緒に暮らす家もあれば、高齢者が集まって暮らす家もあり、スタイルは様々です。
シェアハウスは多くの場合、自分の個室があり、プライバシーは保てます。一方で、キッチンなど共用スペースでは、他の住人と交流することも可能。一人暮らしの寂しさを和らげたり、困った時に助け合ったりという暮らしが実現できます。
私もシェアハウス生活の経験がありますが、「シェアハウスはその家によって雰囲気が異なる」という点を意識すると良いです。
今回紹介したように「他の人と助け合って暮らしたい」と思って入居する人もいれば、ただ単に「家賃が安いから住んでいるだけで、交流は求めていない」という人もいます。シェアハウス探しの際は、どんな人が暮らしているのか、どんな雰囲気なのかを確かめておくと良いと思います。
なお、シェアハウスに入居する以外にも、同じく独身の友人と共同生活をするという方法もあります。
定期的に会う人をつくる
- 趣味、習い事
- 推し活
- 定例飲み会
など、定期的に交流できる仲間をつくるのも一つの手です。
共通点のある、共感できる人たちと定期的に会って話ができるのは大きな心の支えになります。
自分と同じ「独身女性」とのつながりが作れるとなお良し。独身女性ならではの思いを共有し合って、ストレス解消にもつながるでしょう。
地域の人と積極的に関わる
自分の暮らす地域の人と自分から交流し、関係を築きに行く姿勢も大切です。
・地域活動やボランティアに参加する(地域の清掃など)
・地域のイベントに顔を出す(お祭りなど)
・自分の職業経験や得意分野などを人に教える
といった活動を通じて、ただ「その町に物理的に住んでいる」だけでなく、「その町の一員として暮らしている」一体感を感じられるようになります。
ペットと暮らす
ペットを家に迎え、一緒に暮らすという選択肢も。生活を共にする相棒になってくれて、心の安定と癒しが得られます。
また、ペットとの生活は、ペットとの触れ合いそのものだけでなく、人間との交流も深めてくれます。散歩やペット関連のイベント、SNSなどがきっかけになり、対面でもオンラインでも新しい繋がりができることもあります。
まとめ:結婚しない人生を生きるなら、「お金」「孤独」に向き合おう
本記事では、「結婚しない人生を生きる女性の『老後のお金』『孤独』対策」について紹介してきました。
・老後には想像以上にいろいろなお金がかかること
・そのお金を用意するにも時間がかかること
・孤独の解消には、自分から動いて人とのつながりをつくること
など、独身を選ぶと、ちゃんと自分で人生設計をして、能動的に生きていく必要があります。
しかし、それは「自分で人生を自由に設計できる面白さがある」ということだとも思います。現役時代のうちから、「何を対策すべきか」しっかり把握して行動しつつ、身軽で自由気ままな独身生活を楽しんでいけると良いですね。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!